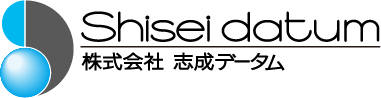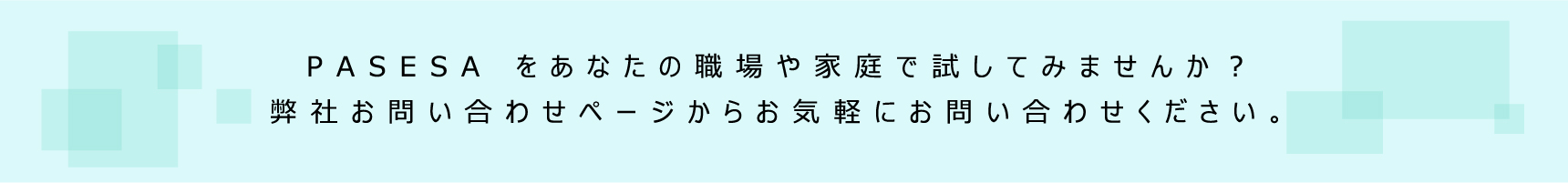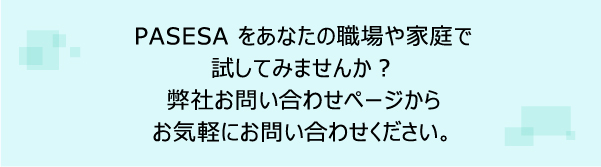わたしたちのカラダの隅々まで
酸素や栄養などを運んでくれる大事な「血管」
明日の元気と健康のため
「血管」のナルホドを学びましょう!
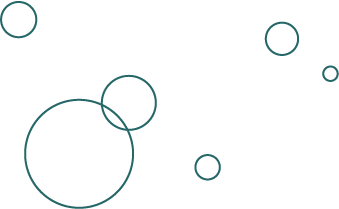
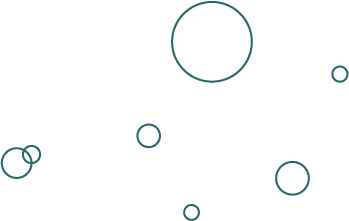
blog
ブログ<5>
来たる2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間にわたってパシフィコ横浜ノースにて、第29回日本心血管内分泌代謝学会学術総会(CVEM2025)が開催されます。
https://www.m-toyou.com/cvem2025/index.html
本会では、心血管内分泌代謝領域および医工連携領域を含むさまざまなプログラムが予定されています。その多くは専門的な医学研究をテーマとしたものですが、シンポジウム3「医工連携」では、パセーサでおなじみの血管指標API、AVIの開発経緯から最新の研究成果、そして社会実装への取り組みをご紹介することになりました。なお、展示コーナーでは、開発中の家庭用パセーサのデモ展示も予定しております。
前回のブログでもご紹介したように、横浜市立大学医学部循環器内科の石上友章 診療教授のグループは、AIが解析したAPI、AVIによる血管年齢が、国際標準の「cf-PWV」に匹敵する、実用的な動脈硬化の評価指標になりうることを示しました。さらに、この指標によって、将来的な心血管疾患のリスクが高い人を早期に発見し、予防的な介入を促すことができるという、臨床現場における具体的なメリットを提示しています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40649096/
弊社は昨年12月に、神奈川県と未病改善に向けた取り組みに関し覚書を締結し、この新たな指標を医療現場のみならず、広く未病社会で活用し、その価値を最大化していくことを目指しています。血管老化のメカニズム解明や、AIやPHR(パーソナルヘルスレコード)を活用した新たな診断・予防法開発に向けて、皆様との共同研究や協業を積極的に模索しております。ぜひブースにお立ち寄りいただき、明日の健康・医療について語り合う機会をいただければ幸いです。
------------------------------------
第29回日本心血管内分泌代謝学会学術総会
シンポジウム3「医工連携」
9月28日(日)10:30~12:00 会場:第2会場(パシフィコ横浜ノース G416+G417)
■患者個別に対応した脳循環代謝シミュレーションの臨床応用の最前線
演者:大島 まり 先生(東京大学 大学院情報学環)
■これからの医工連携
演者:小峰 秀彦 先生(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門)
■オシロメトリック血圧計による血管指標の開発
演者:斎藤 之良(株式会社 志成データム)
------------------------------------
------------------------------------
<血圧計パセーサの最新関連情報>
◆国の「健康・医療戦略(第3期)」に「未病」が盛り込まれました!
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f535999/documents/kenkou_iryo_senryaku.html
◆神奈川県みらい未病コホート研究の全体像と認知機能項目の拡充について
(神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 准教授 中村翔 先生)
ベースライン調査項目(生理学的検査)にAPI、AVIが導入されました。
https://www.youtube.com/watch?v=3xCaNfKKvZY
◆Granstra 【神奈川県未病オンライン展示会】
https://granstra.com/ssr/exh/APqFU7EB4zQ4XnlmRfc5/bt/6QMAf0G9Ttlmpbii97Sc
みなさん、ネットで買い物をすることがあると思いますが、買った商品や製品のアフターケアが必要な時、たとえば、メーカーのウェブサイトを調べたことがありますか?少し前までは、そこに書いてある連絡先に電話したりメールを送ったりしていました。でも最近は、サイト自体にチャット機能が付属していてその場で質問に回答してくれる会社も増えました。賢い「AI(人工知能)」が担当者の代わりに考えるようになったのです。
そんなAIの進歩は医療の世界でも活用されるようになりました。昨年10月の日本高血圧学会学術集会では、横浜市立大学医学部循環器内科のグループが「AIが推定する血管年齢」に関する研究成果を発表し、医学専門誌にも掲載されました。この研究では「API」「AVI」というパセーサの血管指標を用い、AIを使って「血管年齢」を算出しています。
その結果、AIの算出した血管年齢が心臓や腎臓の状態とも関係していることが明らかになり、リスクの高い個人を早期に特定できる可能性があるとのこと。パセーサを利用する方法は、従来の動脈硬化検査よりも手軽に行えるため、病院以外の薬局や職場、家庭などでの活用も期待できます。この論文では、AIの分析によって動脈硬化症の一次予防の精度を上げ、ハイリスク者に限定する現在の医療戦略よりも広範囲にアプローチできることから、集団全体の発症リスクを低減するという戦略へ移行する可能性を指摘しています。
これは集団の発症そのものを遅らせる戦略ですので、健康寿命の延伸も期待されます。当社では家庭用パセーサの上市を急ぎ、世界に先駆けて、今回の研究成果である「AI血管年齢」の社会実装を実現し、民間・行政を問わず積極的な協業を推進することで、国家的な社会課題である健康寿命延伸に貢献してまいります。
都内の大手タクシー会社総務部の新人Aさんは、ドライバーの方々の健康管理用に導入したパセーサで、自身も継続的に血圧や血管年齢の測定を行っています。Aさんは自分のスマホに蓄積された、血圧や血管硬化度のデータと、健診のデータをAIに読み込ませて、日々の健康アドバイスを出力させる実験を行っていました。
AIは収集したデータから、疲労の蓄積やストレスなど、その兆候を教えてくれ、十分な睡眠や休みを取るなど、様々なアドバイスをしてくれるとのことです。現在、データの集積を進め、経営層へ全社的な利用を提案したいとおっしゃっています。
Aさんは文系の大学出身で、医療関係者ではありませんが、最先端研究と同じアプローチで、パセーサの活用を考えておられるということに驚かされました。
昨年の12月、国際的に評価の高いイギリスの学術誌「Physiological Measurement」に掲載されたある論文は、パセーサを開発した当社にとって、とても意義深いものでした。「血管の老化を評価する技術の開発」と題された総論的テーマをとりあげ、脳心血管疾患の医療に必要な血管老化の評価技術の現状と、解決すべき技術課題を報告しているからです。そこでは、以下の4項目が指摘されました。
(1)血管老化の評価技術は、CVDなど臓器障害の診断、予測に役立つ可能性がある。
(2)様々な評価技術・製品が提案されたが、日常的に評価できる装置が開発できていない。
(3)片腕で測れるオシロメトリック方式は有望な技術である。
(4)血圧や年齢で補正することなく、波形のみで評価する方式が望ましい。
つまり「血管老化を評価する製品が有用だが、日常的に測定することができる機器が開発されていない」ということです。しかし、パセーサの血管指標AVI,APIは、血管老化評価に必要な課題の多くを解決している技術であり、既に、50本を超える臨床研究論文において検証されています。
また、前述の論文からは、日常的に血管老化指標の測定頻度を上げ、ビッグデータやAI解析により精度向上を目指すべき、という今後の展望もうかがえます。その意味で、家庭用パセーサは、医療レベルの血管老化指標の測定環境を日常化し、極めて安価な費用で導入できる健康管理機器といえるでしょう。
当社では、2011年の初代パセーサ上市以来、大学病院や研究機関との共同研究を通じて、エビデンスの蓄積を進めてまいりました。近年では、病院やクリニックに加え、薬局や企業の健康経営などへの導入も進んでいます。医療現場から企業や家庭まで、世界に先駆けて「血管老化」の日常的な評価システムを社会実装し、国内外の医療や健康促進を新たな次元に導くよう貢献してまいります。
2024年は、コロナ禍の呪縛から解き放たれたかのように、人々の往来が増え、経済活動も活発化しました。
一方で、能登半島での二重災害、世界各地での戦争、さらには顕在化する異常気象など、心休まることのない1年でもありました。
当社が発明・発見した血管機能指標であるAPIとAVIは、間もなくその誕生から20年を迎えます。
時間の積み重ねが真実を裏切らないことを、改めて実感する知らせがありました。
それは、昨年の日本高血圧学会総会で発表された、APIとAVIを用いたAI血管年齢に関する研究です。
この技術は、既存の健康・医療システムにパラダイムシフトを引き起こす可能性を秘めていると強く確信しました。
今年は、この可能性を検証する「元年」であり、健康寿命の延伸に向けて、パセーサがその本領を発揮するプロローグの年となると確信しています。
今後とも、当社の活動への変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
最近、医療の世界でも画像解析を中心にAI(人工知能)の利活用が急速に進んできました。
心血管疾患の発症予測においても、古典的な多変量解析に代わって、深層学習による予測の有用性が、多数報告されるようになりました。
10月の日本高血圧学会総会では、パセーサの血管指標API,AVIを用いて、血圧、血糖値、LDLコレステロールなどと併せてAIによる解析を行うことで、動脈硬化の高度な発症予測と根本治療に結びつく可能性について研究報告がありました。従来のガイドラインによる動脈硬化の予防は、今後AIと血管指標の導入によって、個別的かつ根本的な治療法へ、パラダイムシフトしていく可能性があります。
家庭用パセーサの製品化により、世界に先駆けて動脈硬化の日常的な見える化が社会実装され、その根本治療を通じて、健康寿命延伸にパセーサが大いに貢献できることを確信しています。